スペアナ・キットの性能面/機能面を、より向上させるべく、GigaStに協賛したスペアナ設計の展望について、ご紹介します。
![]() スペアナ設計の展望
スペアナ設計の展望
スペアナ・キットの性能面/機能面を、より向上させるべく、GigaStに協賛したスペアナ設計の展望について、ご紹介します。
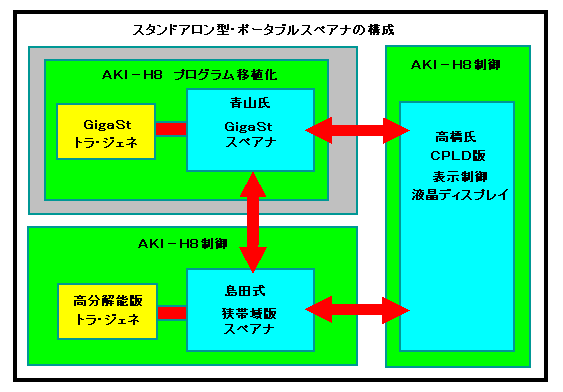 |
| 図1.スタンドアロン型・ポータブルスペアナの提携構成図 |
![]() (2001.1.9)
(2001.1.9)
A/D変換やシリアル通信機能を簡単に扱えるPICが安価に入手できるようになったため、AKI-H8制御ではなく、PIC16F87Xで構成する方針に変更しています。
![]() 狭帯域版スペアナ構想
狭帯域版スペアナ構想
この狭帯域版と言いますのは、スペアナの最小スパン幅の分解能を上げるもので、現在のGigaStスペアナで最小12.5MHzであるスパンを、数100kHzにして観測する1G+2G+オプションUVという構成です。
従来の広域スパン時は現行のUVをそのまま使用し、高分解能時にはオプションUVに切り替えて使用します。格好良く言えばそうなのですが、オプションUVの回路構成はそんな大げさなものではございません。原理的にはダイレクトコンバージョン受信で480MHz帯を低周波域に変換するコンバータです。
主な手順としては、
というように、実に480MHz帯を受信する鉱石ラジオと言った感じです。スペアナの周波数をもう少し細かく見たい人にはお勧めです。
その検波出力は logではありませんが、そこは、QBASICのソフト側で、log10で計算をすればdB表示はなんとか対応できそうです。問題は、480MHzVCOの周波数を安定に掃引する必要があることですが、今回は安価&手軽にできることを目標にしておりますので周波数精度・安定度は落ちますが、あえて
PLL回路は使いませんでした。
実はCXA1315のDA空きポートを480MHzVCOの周波数制御に利用しようと思っています。
8ビットということで255を250通りに設定すれば、2ポート併せて画面横軸がちょうど500個となり都合がよいためです。オプションUVはまだキット完成というところまでは、達してはいませんが、スイープ掃引でオプションUVをオシロスコープで確認した段階では、100kHzスパンまで見て実用になりそうです。
ただし原理上910kHz離れたところにレスポンスが生じるため、今のところ100kHz〜900kHzまでのスパン限定版のオプションとして、少しでもお役に立てればと思っております。
![]() (2001.1.9)〔注〕 1G及び2Gユニットを使用して狭帯域化した場合には、周波数のふらつきが大きいため、現在では、Ver2.0の構想で実施しています。
(2001.1.9)〔注〕 1G及び2Gユニットを使用して狭帯域化した場合には、周波数のふらつきが大きいため、現在では、Ver2.0の構想で実施しています。
![]() 高分解能・狭帯域版スペアナ構想(Ver2.0)
高分解能・狭帯域版スペアナ構想(Ver2.0)
この高分解能・狭帯域版と言いますのは、スペアナの最小スパン幅の分解能をさらに上げるもので、観測する狭帯域版をさらに高性能にし、数100Hzにしたバージョンです。1G及び2Gユニットでは周波数のふらつきが大きいため、新たにユニットを構成します。安定性を重視するため測定周波数範囲は1GHz以下となっています。
主な手順としては、
 |